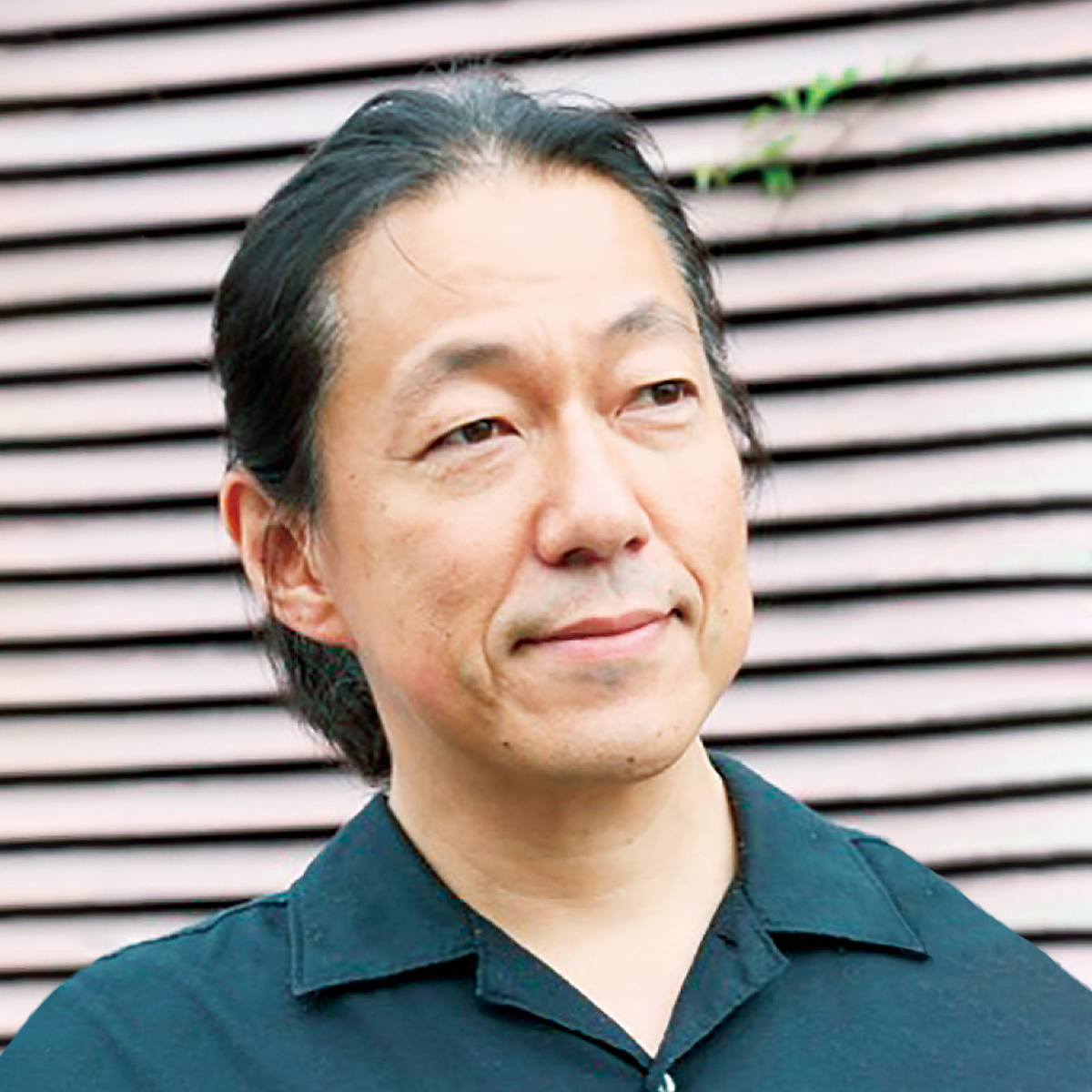2021/07/28
三宅島のイタリアントマト
三宅島で育つ調理用トマト。このイメージを得たのは、ニューヨークで暮らしていた二〇〇一年の晩秋だ。バンド「叫ぶ詩人の会」の活動が休止になり日本を離れたボクは、摩天楼の街で二年目の悶々とした日々を送っていた。この年の九月十一日には同時多発テロがあり、崩れ落ちていくワールドトレードセンターを目撃した。自分の進路もわからず、心が苦しい季節だった。
母国日本のことも気になった。不景気で自殺者が増えているという。その頃、世界でもっとも自殺率の低い国は、お隣のメキシコだった。それならば、メキシコ人の生活習慣や食事を分析することで、気持ちをタフに保つ方法が見つかるのではないか。そんなふうに考え、メキシコ発であり、メキシコ人が毎日必ず食べるもの、トマト、インゲン豆、ペッパーについての勉強を始めた頃でもあった。中でもボクはどんどんトマトにハマっていき、火を通すと旨味が増す調理用トマトのファンになっていた。そこで思いついたのだ。
メキシコでもアメリカでも人気ナンバーワンの調理用トマト「サンマルツァーノ」は、火山灰土を好むという。本場のイタリアではベスビオス火山の麓が名産地であるらしい。それなら、二〇〇〇年に巨大噴火を起こし、島民全員が避難した三宅島でいつか復興のお手伝いができるのではないか。日本では馴染みの薄い調理用トマトだが、マンハッタンではバーベキューで食べさせる店が人気を博していた。この食べ方はやがて日本でも流行るだろう。そのとき、三宅島が調理用トマトで鈴なりになっていたら・・・。
ボクはその翌年に帰国し、メキシコが一番自殺をしない国であることの秘密を書いた本を上梓した。だが、三宅島でトマトを栽培する夢については努めて忘れようとしていた。まだ三宅島は火山ガスが強く、入島禁止になっていたし、なによりも自分の生活に余裕がなかったからだ。
二〇〇七年、ボクはNHKの番組で初めて三宅島に渡った。島民の帰島とともに始まった復興を歌で応援するためである。島との強い縁を感じた。だが、トマトのことは口にしなかった。言ったところで実現できっこないと思ったからだ。
しかし、縁はやはり導いてくれた。二〇一六年春、再び三宅島を訪れることになった。ボクが原作小説を書いた映画『あん』が島内で上映され、主演の樹木希林さんとともにトークショーをやることになったのだ。島に向かう飛行機の中でボクは三宅島とトマトへの思いを語った。だけど絶対に内緒ですよ、とも付け加えた。言ったらやらなければいけないことになるからと。
これが失敗だった。希林さんはトークショーの最中に、「あなた、トマトのことで言いたいことがあるんでしょう」と振ってきたのだ。仕方なく、ボクはこれまで隠していた夢を、数百人の島民の前で語った。言い終わると、雲が一つ生まれそうなほどの熱い拍手に包まれた。これで逃げることができなくなった。この年のうちに島内にアパートを借り、サンマルツァーノの種を農家の方に配り、「栽培しませんか」と呼びかけを始めたのだ。
あれだけの拍手をしてくれた割に、島民の皆さんはボクのことを疑った。政治的野心があるのではないかとも言われた。一年目はなにもできずに終わってしまった。頭に来たボクは、ネズミの巣となっていた古民家を買った。島に住めば、心を開いてくれる農家があるのではないかと思ったのだ。
その結果、東京都の農業試験場と、今や「三宅サンマルツァーノ」のブランド名で出荷に追われる菊地農園さんが手をあげて下さった。調理用トマトを育てた経験はない。どんなものなのか、試しにやってみましょうということだった。
初めての収穫のあと、ボクはトマトの丸焼きを試験場の担当者や農園の若社長に食べてもらった。そのときの彼らの顔が忘れられない。「これは美味い!」と爆発的な笑みが浮かんだのである。
その翌年から、「三宅サンマルツァーノ」の栽培と出荷が本格的に始まった。ホームページを立ち上げ、SNSを利用してのネット販売というやり方だ。なんと、ものの数日で予約完売となってしまった。おそらくは、ニューヨークでの閃きから希林さんの発言、そのあとの悪戦苦闘などの「物語性」が効果的だったのだろう。なにもなかったところから一つのブランドが誕生するためには、物語が必要になるのだ。しかもそれはフィクションではなく、本当の、リアルな話だ。
菊地農園さんの三宅サンマルツァーノは今年も予約で満杯だと聞く。この人気に目をつけ、島内の他の農園でも、調理用トマトの栽培が始まった。それで、あなたはどこで利益を得ているのだ? とよく聞かれる。
いえ、ボクは一円ももらっていません。夢は、トマトたちが三宅島の復興に役立ち、みんなが笑顔になればいいということだけだったのだから。ボクの利益ではない。でも、島の人々と知り合えたことや、夏は海亀と一緒に泳げることなど、トマトから始まった副産物は数え切れないほどある。それにいつかは、自分でも栽培したいと思っているのだ。